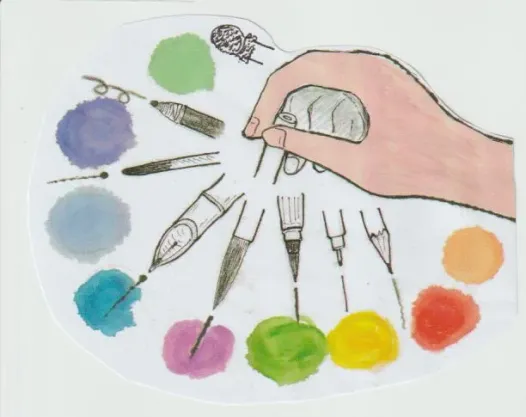子どもが絵手紙を書こうとする活動の場面です。先生や両親に褒められたいという気持ちの子どもの心があります。自分の本当の気持ちを見つめることがなく、他の人の評価を気にする傾向があります。心に感じたことを自由にのびのびと書きたくなるアイデアを紹介します。

褒められたい」「うまく書きたい」という気持ちは自然なことですが、それが強くなりすぎると、子どもが本当に感じていることが表現できません。そこで、、
■ 評価を気にしすぎる子どもに見られる傾向を知っておきましょう。
1.「うまく書けてる?」「この色で合ってる?」と他人に正解を求める
2.人の絵を見てマネしようとする
3.心の中よりも「うまそうに見える絵」「上手に見える言葉」を選ぶ
4.書く前に「なにを、書けばいい?」と聞いてくる
これらは、「感じたこと」よりも「正しく見せたい」「失敗したくない」という気持ちが強く働いている証拠です。
■ 子どもが「自分の気持ちに気づいて、表現したくなる」ためのアイデア
アイデア1. 「絵手紙には上手下手の正解はありません」という安心感を伝える
絵手紙は、うまい・へたじゃなくて、自分の気持ちを絵とことばで伝えるものです。
絵手紙を広めた人が「ヘタでいい、ヘタの方がいい」と言ったので、人気になったんだよ
上手に書こうとしなくていいと繰り返し伝えることで、安心感を与えましょう。
思いやり、優しさが伝わるように願いを込めましょう。
アイデア2. 他人と比べさせない場作り
「みんなちがって、みんないい」という空気を作る
皆さん、自分の顔とこのクラスの人が、全員同じ顔ですか?
同じ顔だったら先生も親もお友達も困ってしまいます。
うれしい時の顔、笑う時の顔も、みんなちがって、みんないいのですよ。
ですから、自分らしく楽しく書きましょう。
自分の感じたことがほかの人と違ってもいい、そしてそれが大切だと気づかせてあげましょう。
違うのは顔だけではありません。気持ちや性格も違います。走ったり動き回るのが好きな子、大きな声で歌ったり笑ったりする子、こわがりで皆の後ろにいるのが好きな子、皆を笑わせるのが好きな子、物まねが上手な子、などあげればきりがありません。
アイデア3.小さな体験や小さな発見を毎日していることに目を向けましょう。
今日は、何年何月何日ですか? あなたの年は何歳何か月、何日ですか?
同じ日はありません。毎日、新しい日になります。新しい自分になります。
新しい発見、学び、体験があります。
今日、おいしかったものは何? どんな味がした?
お家の人、家族は元気でしたか?疲れた顔をしていませんでしたか?
どんなことを話ししてくれましたか?
びっくりしたこと、新しい発見がなかったですか?
今まで知らなかったこと、初めて自分でやってみたこと、ようやくできるようになったことは?

アイデア4.
参考の絵手紙を見せるときも「絵が一番うまい絵手紙」ではなく、「気持ちが現われた絵手紙」を紹介すること
その時の言い方は「感じたこと(気持ち)が伝わってくるね」というコメントをする。
「自分が言われるとうれしくない言葉は書きません。」ここも大切です。
絵手紙は、すぐに消えたりしません。
大人になっても、その絵手紙の言葉が残ることもあります。
自分が言われてうれしい言葉を書きましょう。
それを書く努力をしていれば「いい絵手紙」です。
アイデア5. 「先生も一緒に感じる人」「絵の下手な人」でいる
先生自身が、「感じる人、絵をへたに書く人」であってほしい。次のように言えるかもしれません。
「この間、雨がやんでから、ふと空を見たら、すごくきれいな虹が出ていました。本物のきれいな虹を見たのは何年振りかな、虹を見られてハッピーな気分だったの」
と、感動したことを言葉で言いましょう。
先生は子どもの時から、絵を書くのが苦手だったのよ。
それから、先生の書いた絵手紙を見せると、子どもたちも「こんなことでいいんだ」と心を開きやすくなります。
先生もできるだけへたな絵を書いて見せましょう。(注意点、上手に書かないこと)
生徒に、「ワー、先生へただあ」と言われたら最高の誉め言葉です。成功です。
小学生の上学年(4・5年生)には、自分は何を書きたいのか、自分の心の中を整理できるように
問いかけるように勧めます。急いで書かなくてもいいことを伝えます。
子どもにかけたい一言の例その1(低学年)
1.「お母さんやお父さん、お友だちが言った言葉で、うれしくなったことはあった?」
2.「それ、○○ちゃんしか気づかないことかもしれないね。すごいね」
3.「先生は、その気持ちが伝わってきてドキッとしたよ」
4.「心の中で“これ、描きたいな”って思ったことは、気持ちが冷めないうちにすぐ書いてみよう」
練習用の紙か、メモ用紙に書くのがオススメ
5.「なかなか書きたいことが浮かばないときには、見てもらいたい相手の顔を思いうかベると、書きたいことが出てくるらしいよ」
〇少しの声掛けで、子どもの心は驚くほど素晴らしい反応をします。
自分の絵の評価を求める気持ち(気にする気持ち)は次第に薄れて自然にバランスがとれていきます。
子どもにかけたい一言の例その2(高学年を含む)
1.うれしいこと、たのしいこと、悔しいこと、がっかりしたこと、、笑ったこと、怒ったことを思い出してみよう。(感情の刺激)
2.最近、(または今日)びっくりしたこと、何かある?
3.何かを観察していると、他のものに見えることがあるよ。ほら、空の雲も犬に見えたり、ワニに見えたりするよ。(観察力から想像する)
4.教室の中や外を見てみよう。そして見ているものに語りかけるとおもしろいよ。ランドセル、重いなあ。食べ物、早く食べたいおいしそう。筆箱、鉛筆、消しゴム、机、くつ、バッグなどにも語りかける。
5.自分のことを見て書いてみよう。左手、足、靴片方、隣の人の靴。
6.それいいね、先生それが好き、あなたらしくて素敵だよ、先生にもその気持ちわかるよなどのように、その気持ちがしっかり伝わっていると言いましょう。
子どもが「感じたことはいっぱいある。書きたいこともいっぱいある。どれにしようかな」と思えるように勧めます。いっぱいあり過ぎたら、「絵日記ノートに絵手紙」を書かせましょう。