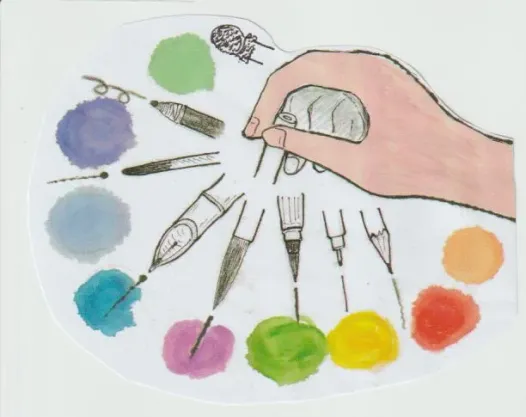教える方法について、次の6項目を説明します。
1.準備編 2.道具の選び方と説明の準備 3.道具の置き方 4.書き方の説明 デモンストレーション 5.完成作品の共有 6.まとめ、片付けと清掃
●この記事はすでに1万3千回ほど閲覧していただいています。さらに詳しいサイトを紹介します。
1.準備編(考え方)
道具の説明から絵手紙を書くという実践活動、そして片付けまでの流れを50分以内に行うためには良い準備が欠かせません。
(目的)絵手紙を子どもたちに教える目的から考え、簡単な目標にしましょう。
図工の科目の一つでしょうか?絵手紙がどんなものか知らせることでしょうか?絵や言葉を書いて、気持ちや思いを伝える楽しさを味わってもらうことでしょうか?相手を思いやる気持ちを絵と言葉で表現することですか?
(考え方) 絵手紙とは身近な道具で、身近なものを題材にして書くものです。そして、身近な人に渡したり送ったりします。これを日本絵手紙協会では、身近主義という表現をされています。そのため、準備の段階から身近なものを利用する方法をお勧めします。
具体的な準備 小学校の図画工作の時間に使っている道具を活用します。家庭ではクレヨンや色鉛筆を使ったり、他の彩色筆記具を使っている子どもも多いかもしれません。もし、教材として水彩絵の具の道具が学校にあればそれを活用することにしましょう。
筆をどれにしますか?葉書きはどれを使いますか?他に準備するもので持参させるものはありませんか?
2.道具の選び方と説明の準備
絵手紙に必要な道具(筆、絵の具、葉書、下敷きなど)を準備し、その使い方を説明します。
筆をどれにしますか?葉書きはどれを使いますか?他に準備するもので持参させるものはありませんか?
1)筆記具は、鉛筆(2Bが書きやすい、無い場合はHBでも可能) ボールペン、油性ペン。
書道用の筆は高学年向きで、書くのに難易度が高く書く時間もかかります。書きやすいのは普段に使っている鉛筆です。消しゴムもあるとよい。
これだけで線描きができますが、少し絵手紙らしくするには、鉛筆で下書きさせてから油性ペンで仕上げる方法があります。一般に、ネットで調べると、書道用の筆で線描きを勧めてめている場合が多くありますが、子どもの年齢を考えるとお勧めしません。後日、子ども自身が絵手紙を書きやすいようにするにも、身近にある鉛筆を利用させましょう。
2)葉書について
葉書きの選び方にも注意が必要です。色の塗りやすいものかどうか、すぐに変形しない厚みがあるか、(身近に厚みのある画用紙があれば、切って作れます。)それらを考慮します。
葉書きの大きさは普通サイズ。もし、もっと大きいサイズの用紙を使いたい場合でも大きくし過ぎないようにしましょう。(色塗りの時間と普通サイズの理解のため)市販の絵手紙用の画仙紙葉書きは、にじみがあるので、小学低学年の子どもには、避けたほうがよいでしょう。
3)彩色する道具 学校の教材が基本、水彩絵の具を使う。絵の具と彩色の筆、パレット。
顔彩は使わない方が良い理由。高価であって、水彩絵の具よりも混色が作りにくい。
5)他に準備するもの。
1.下敷き(新聞紙か書道用の半紙、両方使うこともある)
2.筆洗いの容器。水彩用具の中にあればそれを使用。無いときは紙コップでも代用できます。
3.筆を洗うためと水で色を薄くするための水、が必要です。水を入れた大き目のペットボトルが使いやすい。ただし、各個人に持たせない方がいい。使い過ぎる子どもが多くいるので注意します。
4.テッシュペーパー(折りたたんだものが良い)。筆の水分を吸い取ったり、色塗りの時の色を確かめる時に使用します。
5.汚れた水をいれるバケツ。汚れたゴミ入れの袋などの準備
5)絵手紙を説明するためのメモ。
1.絵手紙は、絵と言葉を書いた葉書(はがき)です。人に送ったり見せたりします。
子どもたちには「ハガキに書く絵日記」と言うと分かり易いようです。
2.絵手紙は、自分の気持ちや考えを書くもので、人と同じになりません。
人と比べないようにしましょう。
3.注意点として、水をこぼさない、絵の具を衣服につけない、書き直しをしないようにするため何をどのように書くかしっかり決めてから、筆を持つようにさせて下さい。
4)画材の準備。
自由な画材にさせるのは書きなれた年令の子どもにしましょう。今回の画材はその季節に手に入りやすいもの、野菜や果物が望ましい。
次の野菜や果物を実際に見て描くことで、観察力を養いながら楽しく絵手紙を作ることができます。
野菜
- トマト: 丸くて赤いトマトは、基本的な形を学ぶのに適しています。
- にんじん: 長くてオレンジ色のにんじんは、直線と曲線の組み合わせを練習するのに良い題材です。
- ピーマン: 緑色で独特の形をしたピーマンは、曲線の描き方を学ぶのに役立ちます。
果物
- りんご: 丸くて赤いりんごは、簡単な形と豊かな色彩の練習に適しています。
- バナナ: 黄色くて曲線の多いバナナは、線の流れを学ぶのに良い教材です。
- 柿: 秋の味覚として親しまれる柿は、独特の形と色合いを描く練習に適しています。
当サイトでは参考のために、野菜果物の作品例を見せるためのものを備えました。
無料で自由にコピーし、拡大して印刷し、見せることができます。許可や報告は不要です。
3.道具の置き方の例
順番どおりに机に置くとよい。
1)題材 2)下敷き・新聞紙またはコピー用紙A5でも代用 3)はがき 4)水の入った紙コップとテッシュペーパー 5)絵の具とパレット 6)筆記用具・鉛筆と消しゴム、彩色の筆・油性マーカー
折ったテッシュペーパー3~5枚。 色を確かめたり水分を落とすのに使います。
水を入れるのは、ほかの用具類をすべて置き終わってからにしましょう。水をこぼす危険を防ぐためです。
用具の置き方例

4.書き方の説明 デモンストレーション
実際の時間の構成を決めておきましょう。(例として)
絵手紙の説明、書き方の説明、(10分)実際に書く、(25分)、皆で書いたものを見てみよう(10分)。先生のコメント(5分)となります。単なる目安です。
絵手紙の書き方の説明、その1。。( 低学年向きに説明 )
1.絵手紙ってなあに? 絵と言葉の書かれた手紙です。ハガキに書きます。
郵便で送ったり、渡したりします。
(今回は、後で自宅でも簡単に書けるような書き方を紹介します。)
2.どんな道具を使うのかな? 今日の場合は、~の道具と鉛筆。
道具の説明はとても大切です。詳しい説明は他の記事を参考にして下さい。
ハガキに筆、マーカー、サインペンなどで絵や言葉をかきます。
絵の具、色を塗る筆、パレット、水入れ、テッシュ、半紙。
3.だれに書こうかな?
家族(父さん、母さん、兄弟姉妹、おばあさん、おじいさん)
ともだち(同級生、先生、近所の人,しんせきの人など)
決まったら、私は~に書きますと、声を出してみましょう。
4.絵はどのように書くの?
絵手紙は線から書きます。
絵手紙では絵を大きく書くことが大事です。
相手に自分の気持ちを伝えるには大きく書いたほうがいいからです。
ハガキからはみだすほど大きく書くと、相手によく伝わります。
よ~く見て、小さいところから書きましょう。
絵手紙は「ヘタでいい」(そっくりに書かなくてもいい)
ここで、デモンストレーション。
実際に大きく書いたものを見せる。(または、はがき大の作品例、コピーなどを見せる)
デモンストレーションの絵の記事 まだ記事に投稿していません。
5.色はどのようにぬればいいのかな?
全部に細かく塗らない方がいい。大体、塗られていればいい。
塗りたい色をさがして、パレットでたしかめ、テッシュでもたし
6.どんな言葉をかこうかな?考えてみましょう。(ヒント)
誰かにありがとうを伝えたい、親切にされてうれしかったこと。
誰かと一緒に何かを楽しんだこと。自分が驚いたこと。
遊んだこと、運動したこと、おどろいたこと、誰かに知らせたいこと。
絵手紙はじぶんの気持ちを書くもの。人のマネをするよりもいいんだよ。
まず、絵手紙を渡したい相手の顔を考えてみよう。じぶんのやってきたことをおもいだす。
なるべく、短いことばでかく。
7.書き終わったら手を挙げて知らせて下さい。なまえのサインを書きます。
名前の1文字をひらがなで書く。
5.完成作品の共有
全員の作品を黒板などに貼り付けます。
子どもたちを作品が見えるように、黒板の前に集めます。
○みんなで、どんなものが書けたのか、お友だちのものを見てみましょう。
とくに、良いと思ったところをさがして、見つけた人から手を挙げて発表してください。
6.まとめの言葉。片付けと清掃
先生からまとめのことば(参考)
きょうは、はじめての絵手紙でした。
一人ひとりの顔がちがうように、絵手紙のかきかたも、できたものも違います。
じぶんのものも、お友だちのものも「良いところを見つけてほめましょう」。
じぶんのきもちを、絵とことばで表すのはむずかしいことです。
しっかりと、あいての人につたわるとうれしいですね。
書いた絵手紙は、持ち帰ってお家の人に見せてあげてください。
もう一つ、だいじなことがあります。
書いたものをよせながら、どうぐやよごれた水をきちんと片付けることです。
片付けることは、つぎの良い絵手紙を書くスタートにもなります。
「どうもありがとうございました」
さらに実践的に小学生に絵手紙を勧めたい方に、関連記事
記事1つ紹介