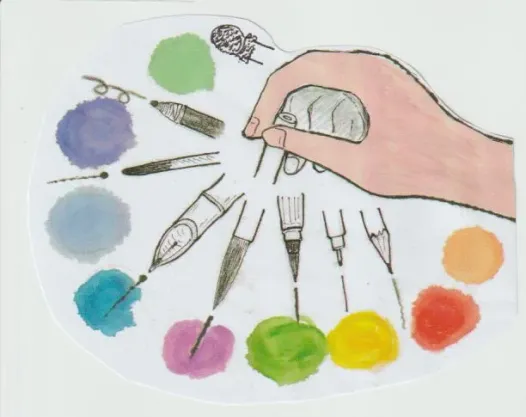東日本大震災から10年経ったという。
マスコミやテレビでも特集が組まれていた。
絵手紙の愛好者一人ひとりにとっても、特別な思いがあることでしょう。
「大震災から絵手紙人は何を学び、どう活かしているか」が問われています。
被災した人の目と、被災しなかった人の目で見ていこう。
大震災はかつてない大きな破壊をもたらしました。
その破壊は津波による原発の破壊にまで及ぼしました。
人命、建物、道路、などを破壊し、さらに人の心まで傷つけ、破壊した。
被災した人ははもちろんですが、被災しなかった人にも大きな喪失感と苦痛を与えました。
そして、この先の未来を「どう生きていくのか」が問われました。
私たちの生き方を根底から見直すように促されました。
大災害の前と後ではものの見方が変化した人が多く、考えなかった人は皆無に近いものでした。
「生きていることの意味」。
救助活動で亡くなった人のある遺族は、なぜ自分が生き残ったのかと自問し続けたという。
また、助けられなかったことを悔やむ人も多い。
私は東北の日本海側である秋田県に住んでいるので、津波の直接的な被害は経験していません。
友人知人がたくさん被災したので、救援ボランテイア活動を少し手伝った程度です。
主に岩手県の釜石市。大槌町が最初です。
津波の被災地は広く長い。
車で走ると瓦礫の山がどこまでも、どこまでも続く。
その惨状の風景が延々と続くことに被災規模の大きさを知らされました。
被災した人にとっては思い出したくない悪夢ですが、被災しない人たちとの格差も目立ちます。
経済的な格差や心に受けた傷の深さというストレス格差もありました。
様々な人の生の声、嘆き、不安を聞く機会もあります。
災害支援金を受取って、パチンコ店に通う人が増えたので、そのことを嘆いている人。
救助活動の自衛隊員もまだ人生経験が浅い20代の人が多いので、死者の姿を見ることは初めての隊員もいる。
まして、津波で流されて瓦礫で傷つけられている遺体は、遺族にとっても若い自衛隊員にとっても見ることだけでもショックが大きい。
殆どの場合は、水に濡れて膨らみ、まるで水を含んだ布団と同じだったと語ってくれた人もいた。
様々な不条理が絵手紙にも表われていました。
様々な不条理と嘆きが絵手紙にも表われていました。
被災した人の絵手紙と、被災しない人の応援の絵手紙には大きな違いがありました。
被災した人たちは経験したこと、実際に見たこと、励まされたこと、心に感動を覚えたことを、取り上げて絵を書いていました。
「生きていてありがとう」「支援に感謝」というものが多いのは当然です。
中には、夫婦の一方が亡くなると、「生き残った方が辛い」「一緒に死ねばよかった」
という本音を漏らす人もおられます。
話を聞くのも辛くなりますが、話すことや文字に言葉を書くことでも落ち着いてくるものです。
中でも、助けることのできなかった後悔の念を引きずっている人が多い。
ある男性の場合は、夜の真っ暗な海岸で海を見ていたら、「助けてください」の声が暗い瓦礫の海から聞こえてきたという。
声だけが何回か聞こえたが、「どうすることもできなかった」と自分を責めていた。
直接、被災しなかった人の心理は?
一方、被災しない方の絵手紙は心の応援です。
被災しない人でも、目の前まで津波と瓦礫が押し寄せたのを見ていた人たちの心理は複雑。
自分や自宅が助かっても、家の中で何日も声を出して笑えることがなく、被害を受けなかったことにうしろめたさがあって、別の苦痛を味わっていた。
被災しない遠方の人の思いはどうだろうか?
私も遠方の絵手紙人から「支援したいので、何でも言ってください」と言われました。
ですが、個人でできることは少なく、公平に届けることや必要な人に届けることは困難でした。
それでも、全国の絵手紙人たちが、それぞれの立場で悩みもがきながら絵手紙を書いて送ってくれました。
私はそれで十分だと思いました。お金やモノは配分が難しいからです。
どんな絵手紙が多かったでしょうか?
被災者が書けないでいる「花」の絵、それに頑張ってとか応援していますという言葉が多い。
どちらも、その時々に応じて「全力で書いた絵手紙」という意味で十分でした。
遠方の人間が見知らぬ被災者に特別な深い言葉を書く必要はありません。
ただ、心配し気遣っている人がいるということを伝えることだけでいいんです。
題材や言葉が違っても、どりらも皆「いい心の絵手紙」でした。
絵手紙を避難所に届ける活動で、気が付いたこと。
その年の7月になってから、日本絵手紙協会から依頼された「絵手紙を届ける活動」に参加しました。
絵手紙とウチワの絵手紙の配布です。
避難所では、食べ物も大分届けられてきて落ち着きを取り戻していました。
絵手紙を届けに来たというので、皆さん喜んで受け取ってくれました。
その状況を、ある友人が「飢饉で飢えている人たちに食べ物を届けている気分だ」と言っていました。
それほど、「我、先に、」と手をのばしていたからです。
それは、「心が飢え、心が乾き、心が求めて止まなかったものだから」と思う。
人は、ストレスのあるときにはなおさら「温かい心の差し入れ」が必要と思うからです。
何よりも明日への大きな栄養剤になったことでしょう。
被災地に絵手紙を届ける前に、地元で絵手紙の展示会をした。
画像、写真などたくさんありますが、省略させていただきます。